私は、トラック運転手をしながら2008年に行政書士試験に合格しました。
合格まで5年、合格率は6%台、当時35歳でした。
この記事を読んでいる人には、トラック運転手をしながらまたは、他の仕事をしながら行政書士試験の合格を目指している人もいるかもしれません。
そんな人に私の経験したことが役に立つなら、こんなに嬉しいことはありません。
暗記マシーン

結論から申し上げますと、暗記マシーンになるしかない!という事です。
行政書士試験は範囲が広く、一定の深さまで覚える必要があり、似通った法律もあるため、正確に覚える必要があります。
私は2008年とだいぶ前に合格しましたが、今も昔も本質は変わってないと思います。
まずは、試験の概要を知ることが必要です。
受験資格・試験日及び時間
受験資格は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験日及び時間は、毎年1回、11月の第2日曜日 午後1時から午後4時までの3時間です。
試験科目と内容等
「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)
・憲法
・行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法を中 心とする。)
・民法
・商法
・基礎法学
の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
「行政書士の業務に関し必要な基礎知識(出題数14題)(令和6年度試験から適用)
・一般知識
・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
・情報通信・個人情報保護
・文章理解
の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
試験の方法
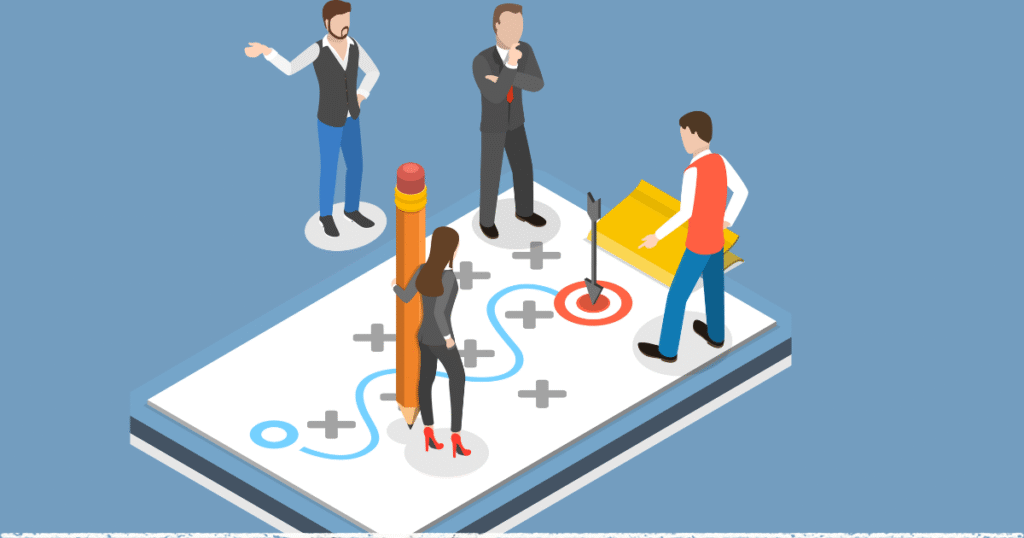
試験は筆記試験によって行います。出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式とし、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」は択一式とします。
試験場所
毎年7月の第2週に公示します。現在のお住まい、住民票記載住所に関係なく、全国の試験場で受験できます。
受験手数料
10,400円
一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。
次に出題形式を見てみましょう。
行政書士試験には3つの出題形式がある
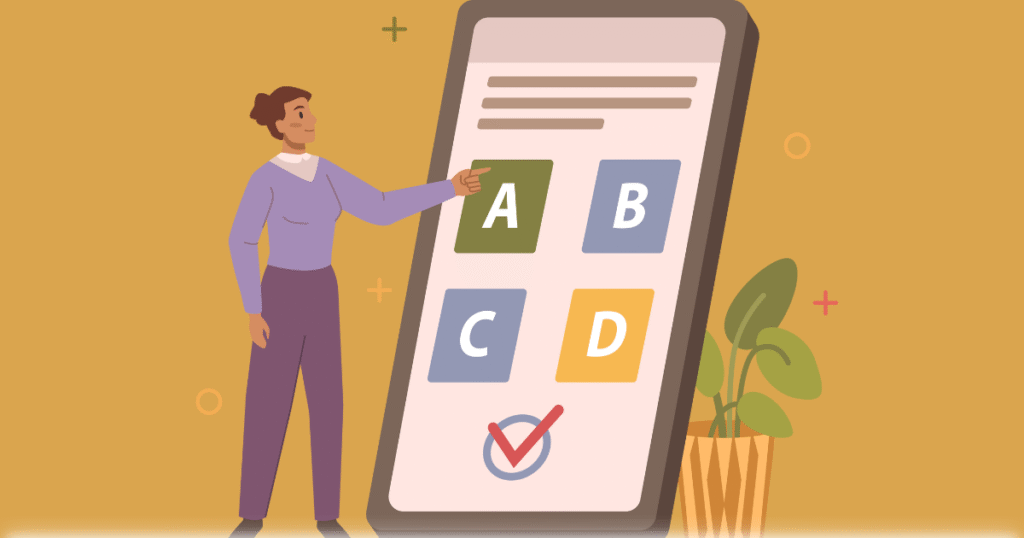
出題形式は大きく分けて、「5肢択一式」「多肢選択式」「記述式」の3種類があります。
「法令等」の科目では「5肢択一式」「多肢選択式」「記述式」の全ての形式が出題されます。「基礎知識」の科目では「5肢択一式」のみが出題されます。
行政書士の試験科目別配点
試験科目別配点は超重要です。
意外と配点を知らない人が多いように思います。
「何を拾って何を捨てるか」「何点あれば合格できるか」など、配点は覚えておきましょう!
行政書士試験の試験科目別配点は以下の通りです。
試験科目 | 出題形式 | 問題数 | 配点 | 出題形式ごとの配点 | 試験科目ごとの配点 | |
法令等科目 (244点) | 基礎法学 | 5肢択一式 | 2問 | 4点 | 8点 | 8点 |
憲法 | 5肢択一式 | 5問 | 4点 | 20点 | 28点 | |
| 多肢選択式 | 1問 | 8点 | 8点 | |||
行政法 | 5肢択一式 | 19問 | 4点 | 76点 | 112点 | |
| 多肢選択式 | 2問 | 8点 | 16点 | |||
| 記述式 | 1問 | 20点 | 20点 | |||
民法 | 5肢択一式 | 9問 | 4点 | 36点 | 76点 | |
| 記述式 | 2問 | 20点 | 40点 | |||
| 商法 | 5肢択一式 | 5問 | 4点 | 20点 | 20点 | |
基礎知識 (56点) | 一般知識 | 5肢択一式 | 1問以上 | 4点 | 4点以上 | 56点 |
| 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 | 5肢択一式 | 1問以上 | 4点 | 4点以上 | ||
| 情報通信・ 個人情報保護 | 5肢択一式 | 1問以上 | 4点 | 4点以上 | ||
| 文章理解 | 5肢択一式 | 1問以上 | 4点 | 4点以上 | ||
| 全合計点 | 300点 | |||||
※「行政書士の業務に関連する一般知識等 」が令和6年度試験より「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」へと変更されました。
※問題数と配点は試験実施年度ごとに変わる場合があります。当該受験年度の正確な配点を保証するものではないため、あくまで目安として捉えてください。
試験科目別合格基準点
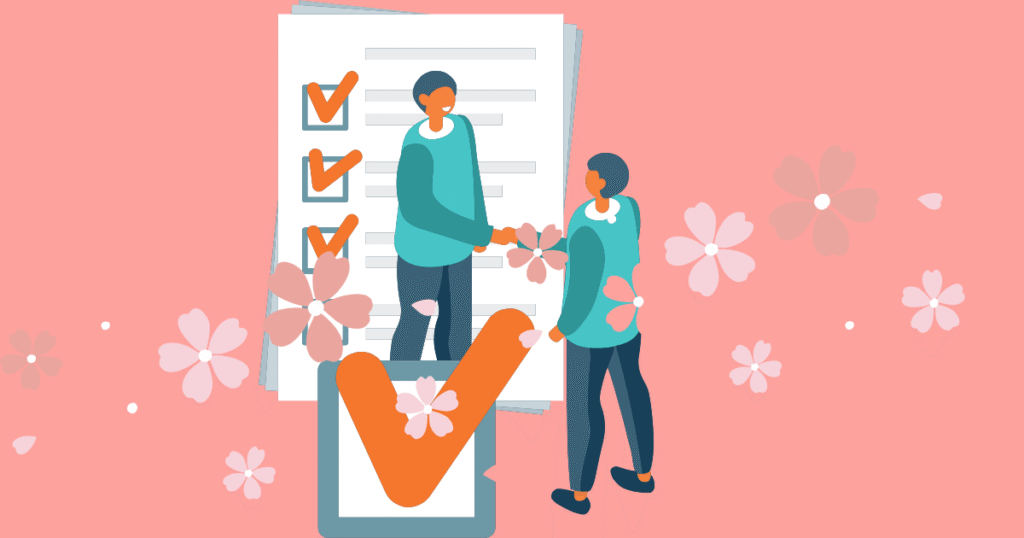
超重要
行政書士試験では合格基準点が定められており、次の要件を全て満たす形で得点を取る必要があります。
- 法令等科目の得点が、122点以上であること。
- 基礎知識の得点が、24点以上であること。
- 試験全体の得点が、180点以上であること。
つまり、法令等科目と基礎知識の合格基準点を両方満たした上で合計点を突破しなければなりません。
配点や合格基準点を理解したうえで、テキストを一読し、過去問をやりましょう。
行政書士・勉強法

テキストを読んでもイマイチよくわからないと思います。
特に商法などは経営などに携わった人以外は、ちんぷんかんぷんだと思います。
そこで無理に苦手な科目で得点しようとせず、好きな科目で得点を稼いだ方が良いと思います。
私の場合、商法が苦手だったので商法はほどほどにして、好きな民法などで得点を稼ぎました。
現に本試験では、商法は1問を得点しただけでした。
また、行政書士試験は浅く広く覚える必要があります。
一定の範囲まで覚えたら、そこから先は試験に合格してから勉強しましょう!
スキマ時間は有効に使う
行政書士勉強法などの本でよく書いてあることですが、スキマ時間は有効に使いましょう!
私の場合はテキストを音読し、それを録音して運転中や寝ながら聞いていました。
荷待ち時間などは、テキストを読んだり、過去問をやったりして、時間を有効に使いました。
働きながらなので、時間を作り出す工夫が求められます。
疲れているときは無理に勉強せず、30分でも仮眠してから勉強にあてましょう!
過去問を5回は繰り返しましょう!
過去問は繰り返し試験に出てきます。
「かたち」をかえて。
「5肢択一式」形式では正解の問題だけを覚えるのではなく、不正解の問題を正しく直して覚えましょう。
正解だけを覚えていくのです。
そして、過去問の正解を覚えたら、過去問に載っていなかった場所をテキストで覚えましょう!
テキストは網羅的に載っているものを買いましょう!
テキスト選びは重要です。
模試試験は必ず受ける!
会場などで模試試験を受験できれば良いと思いますが、会場まで行かなくても図書館などでも良いと思います。
私は図書館でやっていました。
模試試験をやるメリットは、本試験と同様の内容、形式を体験できること。
時間配分を体で覚えることができるのが1番のメリットだと思います。
本試験や模試は過去問と違い、初めて見る形式だったり、文章などが難しく感じがちなどで、そういった意味でも模試試験はとても大事です。
自分がここだと思った学校の模試試験を受験したり、模試試験を取り寄せたりして必ず受けましょう!
わたしが受けた模試の中には本試験の記述問題が出ました。
何のために行政書士試験を受験するのか?

仕事をして、勉強をして、毎日その繰り返しです。
時間を確保するため、飲み会や家族との時間、テレビ、YouTubeなどの楽しい時間を勉強にあてなくてはなりません!
そこまでしてなぜ行政書士試験を受験するのか、信念が問われます。
今まで法律の勉強をしたことがなかった私に法律は、日常にない難しいものでした。
ですが、勉強をしていくうちに慣れてくるものです。
とにかく暗記!意味がわからなくても暗記!その一言ににつきます。
試験合格後のトラック運転手の経験を活かした行政書士業務はあります。
この記事が参考になると思います。

皆さん頑張って下さい。
応援しています。
